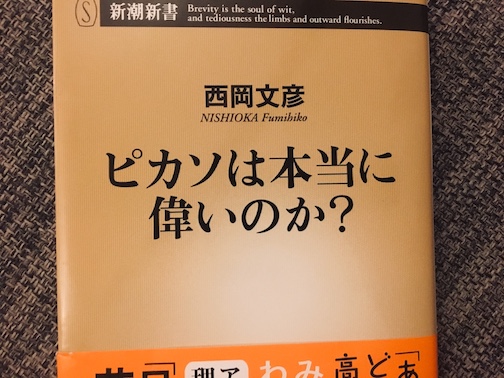
ピカソの絵を観て、どう凄いのだろうかという感想を持ったことは誰しもあるだろう。
本書ではその疑問に対して、人心掌握のカリスマでありビジネスの天才だったピカソが、画商、他の画家たち、彼の恋人たちの間でどんな存在だったのかを紐解きながら、ピカソの画家としての技術力と絵画の歴史の中での位置付けという総合的な視点も交えて答えている。
私が特に印象に残っているピカソの絵は2つある。ひとつは『ゲルニカ』だ。

この作品は、パリにいたピカソが、スペイン内戦で都市ゲルニカがドイツ空軍から無差別爆撃を受けたことを知って描かれたものだ。縦349cm×横777cmの巨大な壁画であり1ヶ月あまりで制作された。苦しみ逃げ惑うものたちが描かれているが、加害者である爆撃機や爆弾それ自体は描かれていない。
壁画はパリの万国博覧会に公開された。後にナチス・ドイツがパリを占拠した際にピカソはパリにとどまっており、アトリエにやってきたドイツ将校に「『ゲルニカ』を描いたのはお前か?」と聞かれた際に「いや、あなたたちだ」と返したと言われている。
私はこの絵を、大塚国際美術館にある実物大レプリカで見た。その時に考えたのは、ピカソは象徴を立てる天才だったのだろうということだった。牡牛、馬、光源、鳥、子供の屍、それを抱く女、駆け寄る女、落ちる女。ゲルニカほど様々な解釈がされた絵画は稀であるといわれているが、たしかにこの絵には”解釈したくなってしまう”力がある。画家自身の想像力以上に、観る人間の想像力を使ってしまうのだ。観る者の知識や経験がそこに「意味」を脳内補完しようとする。たとえば、暗喩や寓意に満ちた聖書はその最たるものだと言えるかもしれない。優れた象徴のまわりには、解釈と、謎と、エピソードや物語が集まってくる。
前衛画家としての旗上げ『アヴィニョンの娘たち』
この本ではゲルニカの話はほとんど出てこないが、ピカソの最大のターニングポイントとして『アヴィニョンの娘たち』 が取り上げられている。
この作品には仮面を思わせる顔が描かれているが、これはパリの民俗誌博物館でアフリカの仮面を見た際に着想したものだという。ピカソが気づいたのは、仮面というものが魔力と呪力をもたらして自分以外に変身するための道具であり、人間を超えた未知なる存在に立ち向かうために魔除けであるということだった。

本書によれば、この『アヴィニョンの娘たち』はピカソが自分自身を前衛画家として世に知らしめ、絵画の未来を担うと宣言するために描いたのだという。そのため、この作品が「わからない」のは当然のことであるという。従来の美しいという概念を破壊するための作品として描かれているからだ。
ピカソ本人が、絵画は破壊の集積であると明言していることからもわかるように、その破壊は明らかに破壊自体を目的としたものでした。それは、いわば確信犯的に行われた破壊であり、そうした破壊の頂点を成す作品が「魔除け」の武器として描かれたという『アヴィニョンの娘たち』であったわけです。
つまり、『アヴィニョンの娘たち』がわからないのは、わからないように描いたのだから当然だと言っているのだ。ピカソが作ったのはつまりは「断絶」であり「落差」であり、それはそれまでの美を破壊しようとした近代絵画の結実であると言える。
題材にヌードが選ばれているのは、アカデミーの伝統において絵画の理論的探求を意味しており、画家にとってヌードを描くことは新しい論文を書くようなものだという。
『アヴィニョンの娘たち』は、ピカソが経済的に安定した後に、入念な準備を経て制作されており、現存している習作だけでも六百点を超えるという。
そこには、ピカソの野心がある。今後の絵画を担う「王」として自分を知らしめたいという思いだ。
画商にあわせて絵を描きわける”驚異的に上手い”ピカソ
私が特に印象に残っている絵の2つめはオルガの肖像だ。

出典:https://www.musey.net/
オルガはロシアのバレリーナでありピカソの一人目の妻である。この絵はオルガから「誰が見ても私だとわかるように描いて」と言われて描いたものだ。ここには、ピカソの代名詞であるキュビズムのわかりにくさは全く無い。素人の私でもわかるほど「普通に上手い」ということが印象的だったのである。
ピカソの技術力という点でみると、多摩美術大学教授である筆者が観たときにピカソは「驚異的に上手い」という。ピカソは父親も画家であり、英才教育を施されたおかげで少年時代からデッサンの達人であった。

出典:https://www.musey.net/
この『科学と慈愛』を描いたのは15歳の時であったという。このような古典的な様式の絵はもちろん、ピカソ中期以降の写実を捨てたような作品にこそ上手さが際立っているのだという。
乱暴に引かれた線やべったり塗られた色面が、じつはこれ以上は考えられないように巧妙に配置され、驚くべき写実性を基盤に描かれている(中略)神がかったまでのデッサン力は、釘で引っ掻いたような銅版画の線などでは戦慄的なまでに発揮され、わずか一本の輪郭線で人体に、筋肉や骨格の構造から、それらをうっすらと覆う贅肉までが描き出されています。
ここまで見事な素描は、ルネッサンスの巨匠による人間離れしたデッサンでも、そうはお目にかかれません。
この「驚異的に上手い」を前提に考えると、ピカソの一連の話がすこし理解しやすい。
まず、ピカソが画商たちの間で前衛画家のホープとして期待されるようになったのは、キュビズムのような難解な絵ではなく、あくまで古典的・写実的な絵画によってだったという。
作品のイメージは、巨匠シャヴァンヌの画風に、ロートレックやゴーギャンといった当時既に一定の評価を確立していた後期印象派の作風をブレンドしたもので、あくまで基本は写実にありました。批評家の中には、そのあまりに巧みな折衷ぶりに、ピカソが器用貧乏に終わることを危惧する向きさえありました。
その上で、ピカソは”カメレオン”のように「その時々の市場の状況に呼応して自身の作風を変幻自在に転換してみせて」いたという。
印象派の販売で定評のある画商には印象派風の作品を描いて渡すばかりか、その画商や家族の肖像まで印象派風に描いているのです。(中略)画風の幅も最先端のキュビスムから印象派のルノワールあたりまでは無論のこと、(中略)ナポレオン時代の巨匠アングルの作風までが含まれています。。しかもそのアングル風のピカソ作品たるや、付け焼き刃などではなく、持前のデッサン力で堂々たる出来にしあげているのだから驚きます。
つまりピカソは何を描けば価値が出るのかに戦略的であったということだ。絵画ビジネスの抜群のセンスを持っていた。そして、それを実現するだけの技術力があったのである。
この技術力はピカソの作品数にわかりやすく現れていて、生涯作品数は油絵だけで一万三千、版画や素描や陶芸など油絵以外では十三万点を超えているという。91歳まで生きたが、毎日描いたとしても一日で五点。ピカソは息をするように絵を描いた。普通に天才だったのである。
近代美術の正統な後継者としてのピカソ
本書では、ピカソが『アヴィニョンの娘たち』に至った歴史的背景が、様々なエピソードともに説明されている。それによれば、ピカソは近代美術の系譜を正統に受け継いだ後継者であったということがわかる。
むしろ異端児だったのは近代絵画の父と呼ばれたセザンヌである。「自然を円筒形と球体と円錐体で捉えなさい」という言葉が知られているが、それは写実から脱却して『抽象する』ことを意味している。

この絵は『石切場から望むヴィクトワール山』であるが、実際には石切場からヴィクトワール山は見えない。二つの景色を合成して描かれたものであるという。物体を立体の組み合わせとして捉え、それを色の面として分解して描いている。
このトポロジー的な「多視点」と「抽象」という(クレイジーな)発想がキュビズムに引き継がれた。ピカソはそれをわかりやすく極端に推し進めて『アヴィニョンの娘たち』という”儀式”を行い、象徴に仕立てあげたのである。
この近代絵画の進展の裏には、写真の登場も大きく影響している。「当時の画家が写真に対して抱いていた危機感は私たちの想像を上回る」ものだったという。
名声を確立してだいぶ経った後にムンクに出会った折りにも、ピカソは写真の出現が絵画の存在基盤を危うくしていると語っています。対するムンクの答がふるっていて、カメラをあの世に持って行き死後の世界を撮れるようになるまでは恐るるに足らないと、一笑に付しています。
タイミングも抜群だった。『アヴィニョンの娘たち』を高値で買い取ったのは画商ヴォラールであるが、彼は絵画が高額で取引されはじめバブルを迎えようとしていたころ、投機対象としてスターとなりうる画家を探していた。
この三年前にゴーギャンが亡くなりセザンヌも健康を害しており、ヴォラールがなんとしても新たな「前衛画家」のホープを確保する必要に迫られていたことも、ピカソに幸いしていた
これ以降、ピカソの絵の価格はインフレしていく。絵画の潮流のなかで様々な流れが合流する地点にちょうどいた天才なのである。
王としてのピカソ
印象的だったのは、ピカソが画家を「王」だと捉えていた、という話だ。ピカソは幼少の頃、生まれ故郷のマラガで大地震に遭い、父親の友人の画家であるドン・アントニオの家に避難させてもらった。この日、ドン・アントニオは不在にしていたが、彼の帰宅のタイミングがちょうど当時の国王が慰問のために街を訪れたのと重なったことで、街で無数の旗で飾られ、馬車を連ねた華やかな王の行列が進行するのを、画家ドン・アントニオの帰宅を祝うものと錯覚してしまったという。
避難はしたものの、家の主の不在に加えて、避難先で心細い思いをしていたピカソの家族に、ドン・アントニオの帰宅は大きな安堵を与え、なによりその帰宅を祝うものと錯覚された行列の華やかさで、幼いピカソを圧倒してしまいます。この錯覚により、幼いピカソは画家は王であるとの認識を抱いてしまい、彼の生涯にわたる芸術家観というものを決定してしまうことになります。
バルセロナを出てパリに向かう十九歳のピカソは、記念に描いた自画像に「われは王なり」と書き入れています。
この「王」というワードは、ピカソという画家を考えるのに不可欠な視点だ。ピカソの妻の一人であるジャクリーヌ・ロックは制作中の夫への面会を断るのに「太陽は邪魔されるのを望みません」と言っていたという。
ピカソは人心掌握の天才であり、その対象は女性相手だけでなく、画商や批評家、キュレーター、ジャーナリストに対しても心理作戦を講じてコントロールしていたという。
画商がアトリエにやって来る前に、ピカソは決まってフランソワーズを画商に見立て、えんえんと想定問答を繰り返したというのです。場合によってはピカソが画商の役を演じることもあり、考えられるやりとりをすべて予習してから本番の交渉に臨んだ
ピカソは平気で前言をひるがえす気分屋で、予測不能で相手を幻惑させるのが常だったというが、そこには周囲を振り回して支配下におこうとするピカソの「王」であろうとする戦術がある。
ピカソ最大の作品=『ピカソ』という偶像
ピカソは『ピカソ』という王となることに意識的であり、そしてそれが天才的に上手かった。『アヴィニョンの娘たち』はその旗上げの作品であり、『ゲルニカ』はその最たる発揮であると言える。
本書ではあまり触れられていない『ゲルニカ』をことさらに取り上げたのは、そこにまつわる物語をふくめて『ピカソ』という偶像が世に広まり伝わるための補助線となり、聖書の役割を果たしていると思うからだ。
それはつまり『アヴィニョンの娘たち』が理解不能すぎることを意味している。『ゲルニカ』がその描かれた動機と物語をふくめてまだ人々の理解の範疇にある一方で『アヴィニョンの娘たち』は”美しくなさすぎる”。少なくとも美しいという言葉では理解できない。そして、理解できないということこそがこの絵における発明であり、それまでの絵画の歴史=美の歴史に大きな断絶を作ったのだと言える。
ピカソ以降、破壊という方角において、ピカソ以上の断絶はもう作りようが無い。破壊それ自体をピカソが絵画にしてしまった時点で、以降は二番煎じにしかならないからだ。絵画はもうすでにピカソに破壊されてしまった。以降、破壊を主題に匂わせる絵画は残ったその欠片を細かく砕いているだけに見えてしまう。ピカソほど世の中に名が知られている画家はその後は出ていないし、今後も出る見込みはおそらく無い。
上では触れなかったが、本書を私が楽しく読めたのは、ピカソのその人柄のエピソードが満載であったことが大きい。ピカソは奔放な女性関係を持ったことでも知られているが、複数の妻や無数の恋愛相手とのエピソードに事欠かない。

そして、それらエピソードもろもろを含めて、ピカソという偶像は一つの作品として大変に魅力的だ。
私たちが物語を食べて生きているのだとしたら、ピカソという画家は、その作品だけでなく生き方や人間性までも含めて史上最大の画家だったと言えるのではないだろうか。

